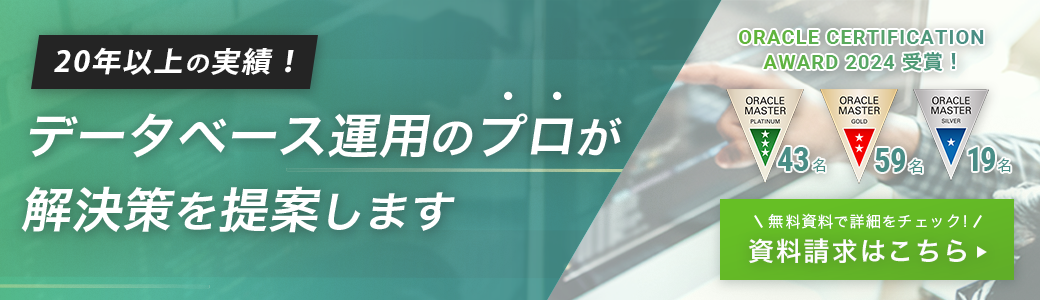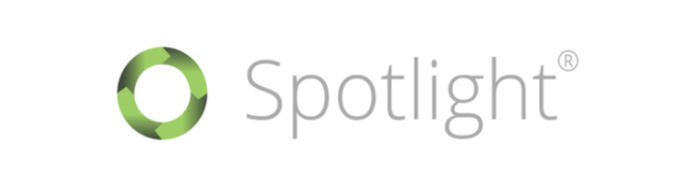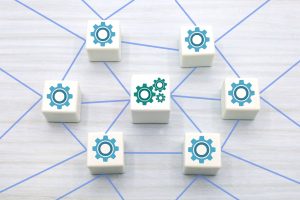システムをオンプレミスからクラウドに移行する際、有力な選択肢の一つとして挙げられるのがOracle Cloud Infrastructureです。
しかし、Oracle社のホームページを見ると、膨大な情報が掲載されており「他社サービスとの違いがわかりにくい」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事ではOracle Cloud Infrastructureについて、サービス構成や特徴など要点を整理して解説します。
情報を精査して自社に最適なクラウドサービスを選びたい方は、最後までご覧ください。
目次
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)とは?
Oracle Cloud Infrastructureとは、Oracle社が手掛けるパブリッククラウドサービスのことです。
パブリッククラウドは、クラウドサービスの一形態で、不特定多数のユーザーに対してサービスを提供するものを指します。
このようなサービス形態の多くは、従量課金制を採用しており、利用人数や用途に応じて柔軟にコストを最適化できるのが特徴です。
そんな利用形態をとるOracle Cloud Infrastructureのサービス内容は、大きく“インフラ環境の提供(IaaS)”と“プラットフォームの提供(PaaS)”の2つに分けられます。
サービス内容の詳細は後述しますが、これらがクラウド上に用意されているため、利用者は高額なソフトを購入したり、面倒な保守作業を行ったりする必要がありません。
Oracle Cloud Infrastructureは、代表的なクラウドサービスである“Amazon Web Services”や“Microsoft Azure”よりも新しいサービスのため、シェア率はこれらに劣ります。
しかし、既存のサービスに足りなかった機能を備えており、その使い勝手の良さから高い成長率を誇っています。
Oracle Cloud Infrastructureのサービス構成
Oracle Cloud Infrastructureは、先述のように“IaaS”と“PaaS”の2つでサービスが構成されます。
さらにIaaSとPaaS内でも、サービスが細分化されており、ユーザーは必要に応じて各サービスを自由に組み合わせることで、自社のニーズに合わせて利用できます。
以下で、この2つのサービスの内容を確認していきましょう。
IaaS(Infrastructure as a Service)
IaaSは、ITサービスの運営に必要なインフラ環境をインターネット経由で提供するサービスです。
具体的なサービスの種類として、以下が挙げられます。
【IaaSに含まれる主なサービス】
| 種類 | 概要 |
| コンピュート | 仮想的なリソース(仮想CPUやメモリなど)を利用して構築される仮想サーバーのこと。これにより柔軟かつ拡張性のあるコンピューティング環境を提供する。 |
| ネットワーク | クラウドを利用するためのネットワークやネットワーク関連機能を提供する。 |
| ストレージ | クラウド上にデータを保存するサービス。インターネットがあればどこからでもアクセスできる。 |
| セキュリティ | 自動化されたセキュリティ体制が構築されている。アクティビティを監視して、問題があれば原因の特定から是正、通知まで自動で実施する。 |
オンプレミスでこうした機能を備えたインフラ環境を整えるには、システムの稼働に必要な機材の準備や構築、運用までを自社内で行う必要がありました。
IaaSでは、クラウド上ですでにインフラ環境が整備されているため、初期費用やハードウェアの維持管理コストを削減して、低コストで利用できます。
また、サーバーを利用する際にハードウェアのスペックやOSを自由にカスタマイズ可能で、自社の目的に合わせて柔軟にシステム環境を構築することも叶います。
PaaS(Platform as a Service)
PaaSは、システムを稼働させるために必要なハードウェアやOSなどが揃ったプラットフォームを、クラウド上で提供するサービスのことです。
同サービスを利用すれば、ハードウェアやOSを自社内で構築しなくてよいのはもちろん、管理する必要もありません。
Oracle Cloud InfrastructureのPaaSに含まれるサービスは、以下の通りです。
【PaaSに含まれる主なサービス】
| 種類 | 概要 |
| 開発環境 | アプリケーションの開発者向けに、設計に必要なツールやプラットフォームを提供する。これにより、クラウド上でのアプリケーションの構築や稼働、管理を容易にする。 |
| データベース | データベースを稼働させるための基盤や機能を提供する。“Autonomous Database”という日常的な管理タスクを自動化するサービスを利用すれば、データベースの運用コストを大幅に削減可能。 |
| アナリティクス | データ分析のために必要なプラットフォームや機能を提供する。 |
| 機械学習とAI | 事前に構築された機械学習やAIモデルのデータを処理するためのプラットフォームを提供する。これにより構築済みのAIをアプリケーションに組み込んだり、独自のAIモデルを構築・学習したりできる。 |
| アプリケーション統合 | クラウドとオンプレミスのデータやアプリケーションを統合するためのツールを提供する。クラウド・オンプレミス間はもちろん、アプリケーション間の連携を円滑化する役割がある。 |
このなかでも、特にデータベースの分野では、Oracle社は世界的なサービスであるOracle Databaseを長年手掛けており、豊富な技術と経験を有しています。
オンプレミスからの互換性が高いうえ、ほかのクラウドサービスよりも柔軟かつ幅広い用途に対応できる仕組みが整えられています。
Oracle Databaseをこれまで利用してきた、またはこれから利用したいと考えているユーザーにとってOracle Cloud Infrastructureは有力な候補になるでしょう。
Oracle Cloud Infrastructureの特徴
Oracle Cloud Infrastructureのサービス内容を見てきましたが、ここからはサービスの特徴や他社サービスとの違いを通してさらに深掘りしていきます。
Oracle Cloud Infrastructureの特徴
- セキュリティ体制が整備されている
- SLAによる保証の範囲が広い
- 高可用性を実現している
- 環境の構築が容易にできる
- コストパフォーマンスが高い
- 高性能なデータベースが使える
それでは順に詳細を確認していきましょう。
セキュリティ体制が整備されている
Oracle Cloud Infrastructureのセキュリティは非常に堅牢で、サイバー攻撃や不正アクセスといった脅威から情報を守ってくれる高い防御力をもっています。
以下に同サービスがセキュリティ体制を強化するために、取り組んでいる主な項目をまとめました。
【Oracle Cloud Infrastructureによるセキュリティ強化のための取り組みの例】
| 名称 | 概要 |
| 顧客の分離 | ユーザー同士のアプリケーションや情報資産を完全に分離して展開・配置する。 |
| データの暗号化 | 暗号化技術によって保存中および転送中のデータを保護する。 |
| 可視性 | モニタリング機能によってログやセキュリティリスクを監視する。 |
| 高可用性 | 複数の独立したデータセンターに情報を保管することで顧客の事業継続性を確保する。 |
上記の取り組みにより、非常に高水準なセキュリティを実現しており、そのレベルの高さは“ISMAP”に対応していることからも裏付けられます。
ISMAPとは、政府が利用する情報システムを決定するためのセキュリティ評価制度のことです。
政府機関が安心して利用できるクラウドサービスを選定するために、ISMAPによって一定の基準を設けて評価・登録を実施しています。
Oracle Cloud Infrastructureは、このISMAPに対応していることから、公的に認められるほどセキュリティレベルが高いことがおわかりいただけるはずです。
公的機関と同レベルの機密情報を扱うようなセキュリティ要件が厳しい企業であっても、安心して導入できます。
SLAによる保証の範囲が広い
SLA(Service Level Agreement)とは、サービスの提供者が、一定の水準のサービス品質や内容を保証する契約のことです。
この契約自体は多くのパブリッククラウドサービスに設けられていますが、Oracle Cloud Infrastructureにおいて特筆すべきは、その保証範囲の広さです。
Oracle Cloud Infrastructureでは、このSLAを“可用性・管理性・性能”の3つに対して保証しています。
ほかのパブリッククラウドサービスでは主に可用性(システムを停止せずに提供しつづける能力)のみを保証の対象としています。
しかし、同サービスでは、サービスを常に管理可能な状態にする管理性、サービスの一定のパフォーマンスのことを指す性能にまで保証が及ぶのです。
こうした保証範囲を広く設定する姿勢からは、“高品質なサービスである”という自信がうかがえます。
ユーザーとしては、事前にサービスの水準や内容を確認できるので安心です。
高可用性を実現している
Oracle Cloud Infrastructureは可用性が高い点も、大きな特徴の一つです。
現代のビジネスでは、システムを24時間365日稼働することが大前提となっています。
オンラインサービスの運用やデータ分析など、システムが停止すると業務に深刻な影響を及ぼす可能性があるためです。
そのため災害やトラブルにより、システムの停止や誤作動があってはなりません。
Oracle Cloud Infrastructureではこうした影響を受けないよう、システムを“リージョン”“アベイラビリティ・ドメイン”“フォールトドメイン”の3つで構成しています。
システムを3層構造にすることで、何か問題が生じたとしてもほかのシステムに切り替えて、稼働しつづけられるようにしているのです。
これにより、Oracle Cloud Infrastructureの可用性は、正しい手順を適切に実施することで99.5%を達成できるとされています。
環境の構築が容易にできる
Oracle Cloud Infrastructureは、「専門知識が必要ない」といわれるほど環境の構築が簡単です。
同サービスでは、システムのリソース作成のツールとして、“Oracle Cloud コンソール”が提供されています。
このOracle Cloud コンソールは、WebブラウザのGUIによって、ユーザーが直感的に操作できる設計になっているのが特徴です。
マシンタイプやデータベース、ノード数などをGUI上で選択するだけで、必要なシステム環境を簡単に構築できます。
このような設計により、Oracle Cloud Infrastructureは専門的なスキルに依存せず、幅広いユーザーが利用可能なサービスとなっています。
コストパフォーマンスが高い
Oracle Cloud Infrastructureは、サーバーやネットワーク機器を収容するデータセンターを小規模に設計しています。
これにより、ユーザーの使用頻度が高いコンピュート・ネットワーク・ストレージのサービスを、他社に比べて低価格で提供することを実現しています。
参考にOracle社が掲載している、他社サービスと価格を比較したデータを次の表にまとめました。
【Oracle Cloud Infrastructureと他社サービスの価格比較】
| Oracle Cloud Infrastructure | 他社サービス | |
| コンピュート | 一時間ごとに41.44円
Compute (VM.Standard2.8,16vCPU,120GBメモリ,Linux) |
一時間ごとに124.99円
仮想マシン (16vCPU,64GBメモリ,Linux) |
| ネットワーク | 月額22,134円
FastConnect (1Gbps,100TB) *閉域網接続 |
月額603,686円
FastConnect (1Gbps,100TB) *閉域網接続 |
| ストレージ | 月額5,950円
Block Volume (1TB,25K IOPS) |
月額278,880円
ブロック・ストレージ (1TB,25K IOPS) |
ほかにも、データの活用や他サービスとの連携の際に重要になってくる、外部へのデータ転送もリーズナブルに利用可能です。
一般的なクラウドサービスのデータ転送は、月間100GBまで無償になりますが、Oracle Cloud Infrastructureでは月間10TBまで無償です。
無償枠を超えたとしても、他サービスの相場では1GBあたり12~16円のところを、3.5円で利用できます。
コストを抑えてパブリッククラウドサービスを活用したいのであれば、魅力的な選択肢となるでしょう。
参照元:Oracle社「後悔しないクラウドのコスト最適化 考慮すべき3つの要素」
高性能なデータベースが使える
Oracle Cloud InfrastructureはOracle Databaseを手掛けてきたOracle社が提供するサービスだからこそ、高性能なデータベースを利用できるのも大きな特徴です。
クラウドサービスのなかでも、同サービスのみで利用できるものに、Autonomous Databaseがあります。
このサービスのポイントは、ユーザーがアクセスできる範囲がデータベース部分のみに限られている点です。
OSより下のレイヤーは、Oracle社によって管理されており、データベースのパッチ適用やバージョンアップを自動で行ってくれます。
これにより、手動の場合にかかっていた労力を大幅に削減可能です。
また、Autonomous Databaseはデータベース内部で、AIの機械学習を利用した自動運用が実施されているため、チューニングといった運用自体も一部不要になります。
この自動チューニングにより、ユーザーはデータベースの運用負荷を軽減しつつ、高速な処理により効率的に作業を進められます。
Oracle Cloud Infrastructureを導入する際の注意事項
冒頭で説明したように、Oracle Cloud Infrastructureは代表的なパブリッククラウドサービスと比べると、シェア率は劣ります。
それゆえに、インターネット上に掲載されている情報量が少ないため、導入時に自力で疑問や問題を解決していくのが難しいという側面があります。
疑問点を残したまま作業を進めれば、導入までに時間を要するうえに、ここまで紹介してきた魅力を最大限に享受できない可能性もあるでしょう。
そのため、もし自社で導入することに不安を感じる場合には、Oracle Cloud Infrastructureの導入支援を行っている企業に相談することをおすすめします。
これらの企業では、導入経験豊富なエンジニアが在籍しており、要件分析から設計、実装、さらには運用サポートまで幅広い支援を提供しています。
この支援により、最適なクラウド環境を迅速かつ確実に構築することが可能です。
Oracle Cloud Infrastructureはセキュリティ・可用性に優れている点などが魅力
本記事では、Oracle Cloud Infrastructureを、サービス構成や特徴から解説しました。
Oracle Cloud Infrastructureとは、Oracle社が手掛けるパブリッククラウドサービスのことです。
サービスはIaaSとPaaSで構成されており、ユーザーは必要な機能を選び、導入することで、自社に合ったクラウド環境を構築できます。
堅牢なセキュリティ体制と高いコストパフォーマンス、そして高性能なデータベースサービスを有している点が主な特徴です。
こうした点に魅力を感じて、導入を検討しているのであれば、コーソルにご相談ください。
プロのエンジニアがお客様のご要望をうかがい、クラウドの設計から構築、運用までをサポートいたします。