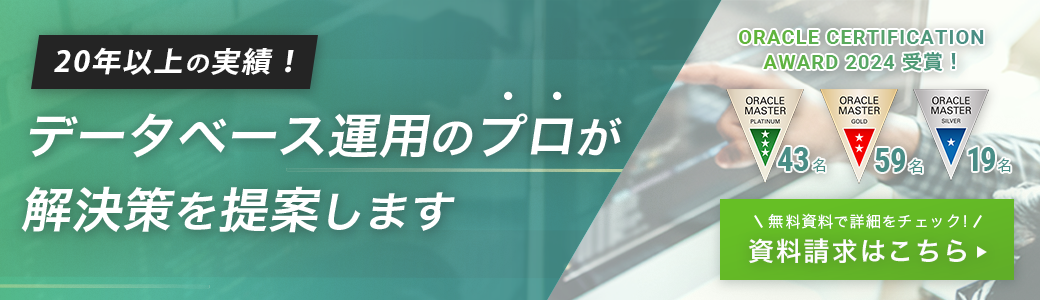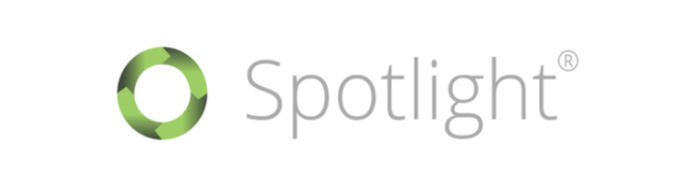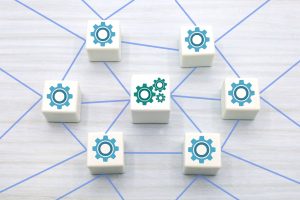Oracle Databaseを利用していても、ライセンスの考え方や費用の算出方法を理解している方は少ないのではないでしょうか。
同データベースは、エディションやライセンスの種類によって考え方が異なり、それぞれOracle社から提示されているルールに基づいて費用を算出する必要があります。
本記事では、Oracle Databaseのエディションや算出方法を徹底解説します。
すでにご利用されている方も、これから導入をお考えの方もぜひ最後までご覧ください。
目次
オンプレミスのOracle Databaseのエディション
現状オンプレミスのOracle Databaseで手に入れられるエディションは、“Enterprise Edition(以下、DB EE)”と“Standard Edition 2(以下、DB SE2)”の2つです。
また、現在は販売終了となっていますが、“Standard Edition(以下、DB SE)”と“Standard Edition One(以下、DB SE1)”もあります。
以下では、各エディションの概要を説明します。
Enterprise Edition(DB EE)
DB EEは、大規模なシステム向けのエディションです。
問い合わせ集中処理型データ・ウェアハウスや、インターネット・アプリケーションなどに不可欠な、パフォーマンスや可用性、スケーラビリティ、セキュリティを提供します。
そしてDB EEでは、追加料金を支払うことで、さまざまな拡張機能を追加できるのが特徴です。
自社に必要なサービスをカスタマイズすれば、柔軟にデータベースを最適化できます。
なお、詳しくは後述しますが、DB SE2にかけられているような制限事項は、DB EEには存在しません。
Standard Edition 2(DB SE2)
DB SE2は、中小規模のシステムに向いているエディションです。
ワークグループや部門レベル、Webアプリケーションに対して、優れた操作性やパフォーマンスを発揮します。
ただし、DB EEと異なり、DB SE2には以下のような制限がかけられています。
DB SE2の制限事項
- オプションを購入・適用できない
- 搭載可能なソケット数が2つ以内の機器にしか適用できない
- 1つのデータベースで使用可能なCPUスレッドは16まで
搭載可能なソケット数について、たとえば実搭載プロセッサー数が2つであっても、ソケット数が4つの場合には、DB SE2は利用できません。
そのため、このような状況の場合はDB EEを選択することが求められます。
以上のように、DB SE2には使用に際して制限があるので購入する際は、自社にとって十分なスペックなのかどうかをきちんと確認しておきましょう。
すでに販売終了となったエディション
先述の通り、DB SEとDB SE1に関しては、すでに販売が終了しています。
ですが現在も利用されている方に向けて、その違いを表にまとめました。
販売中のDB SE2とあわせて、比較してみてください。
【SE・SE1・SE2の機能の比較】
| DB SE | DB SE2 | ||
| 搭載可能な最大CPUソケット数 | 2 | 4 | 2 |
| サーバー1台あたりの最小ユーザー数 | 5 | 5 | 10 |
| 使用可能な最大CPUスレッド数 | 設定なし | 設定なし | 16(RAC構成の場合は各サーバー8) |
| RACの使用可否 | 不可 | 可 | 可(18cまで) |
| RACの最大ノード数 | 4 | 2 | |
| Oracle Database 12.1.0.2の使用可否 | 不可 | 不可 | 可 |
DB SEおよびDB SE1の最終バージョンは12.1.0.1となっていますので、12.1.0.2以降のバージョンを利用したい場合は、SE2を購入する必要があります。
Oracle Databaseのライセンスの種類
Oracle Databaseのライセンスは、“Processorライセンス”と“Named User Plus(以下、NUP)ライセンス”の2種類から選択します。
以下で、一つずつ概要を説明しますので、それぞれの特徴をご確認ください。
Processorライセンス
Processorライセンスは、利用する人数が多い場合、あるいはWebシステムやインターネットなどで利用人数がカウントできない場合に選ぶことをおすすめします。
必要なライセンス数はOracle Databaseをインストールするサーバーに搭載するプロセッサー数に比例します。
したがってプロセッサーを増設すれば、利用人数やクライアント台数の増加にも制限なく対応できるというわけです。
Named User Plus(NUP)ライセンス
利用する人数が限定、また特定できる場合にはNUPライセンスが向いています。
NUPライセンスは、サーバーにアクセスする可能性がある利用者数で、ライセンス数が割り出されます。
これがコストの最適化につながり、Processorライセンスと比べてリーズナブルに利用できるのが特徴です。
なお、利用人数としてカウントするのは、“サーバーにアクセスする可能性がある利用者の総数”です。
同時接続数やクライアント台数などによって、カウントされるわけではありません。
オンプレミスにおけるOracle Databaseのライセンス数の算出方法
オンプレミスのOracle Databaseのライセンスは、エディションとライセンスの種類、そしてそれぞれの算出ルールによって算出方法が異なります。
ここで解説する、それぞれの考え方から割り出すライセンス数は、購入時の価格にも直結しますので、きちんと押さえておきましょう。
Processorライセンスでは、DB EEとDB SE2に考え方が分けられます。
DB EEは、搭載している“総コア数×コア係数”という算出ルールに基づいて、ライセンス数を求められます。
コア係数とは、Oracle社によって定められたライセンス数を算出するための係数のことです。
たとえば、Intel XeonのCPUで8コアを搭載したサーバーで、DB EEを利用すると想定します。
Intel Xeonのコア係数は0.5と定められているため、これを算出ルールに当てはめると“8×0.5”になり、必要なProcessorライセンス数は4本ということがわかります。
そしてOracle社が公開している価格表から、DB EEのProcessorライセンスの価格をチェックし、割り出した本数分のライセンスを購入する、という流れです。
一方で、DB SE2の算出方法は比較的単純で、CPUソケット数がライセンスの数です。
NUPライセンスの場合、エディションにかかわりなく利用人数に応じてライセンス数が算出されます。
ただし気をつけておきたいのが、“最小NUPライセンス数”というルールが定められている点です。
DB EEの場合、CPU数ごとに25ユーザーぶん、DB SE2の場合で、サーバーごとに10ユーザーぶんのライセンスを最低でも購入する必要があります。
たとえば、前述と同じく8コアのIntel Xeonの場合だと、“8×0.5×25”の計算式となり、最小のNUPライセンス数は100ライセンスとなります。
オンプレミスのOracle Databaseで高可用性を実現するためのライセンスの考え方
データベースは日常業務に不可欠なものであるため、常に稼働しつづける“高可用性”が求められます。
Oracle Databaseで高可用性構成を叶えるには、RACとHAのいずれかの可用性を保持するためのシステムを構築する必要があり、それぞれでライセンスの考え方が異なります。
RACとは、障害ノードを自動的に切り離すことでシステムの継続を可能にした高可用性システムです。
全サーバーがアクティブなため、すべてのサーバー分のライセンスを確保しなければなりません。
一方、HAは、アクセシビリティと稼働時間を最大限実現できるように設計されている高可用性システムのことで、以下の条件を満たす場合にはStandby側のライセンスは不要です。
HAにおけるStandby側のライセンスが不要になる条件
- クラスタ構成であること
- 共有ディスクを利用した構成であること
- 待機サーバーでのOracle Databaseの稼働日数が年間10日以内であること
なお、Oracle Database 19c以降において、RACはDB EE限定でつけられるオプション機能となっています。
DB SE2では、HAのみ使用可能です。
Oracle Databaseをクラウドで利用する際のライセンスの扱い
Oracle Databaseは、オンプレミスからクラウド環境に移行して利用することもできます。
では、その際のライセンスの扱いはどのようになるのでしょうか?
以下では、クラウド環境でのライセンスの扱いについて、2つのパターンを紹介します。
ライセンス込みのサービス(LI)の
Oracle Databaseをクラウドで利用するシンプルな方法は、ライセンスがすでに含まれているサービス(License Included)を使うことです。
この方法では、クラウドの利用料にライセンス費用も含まれているため、“単価×利用時間”というかたちでコストを算出できます。
オンプレミスのOracle Databaseのライセンスを持ち込む(BYOL)
すでにオンプレミスでOracle Databaseを利用している場合は、既存のライセンスをクラウドに持ち込むことができます。
この方法を、“BYOL(Bring Your Own License)”とよびます。
ProcessorとNUPのどちらのライセンスでも、BYOLが可能です。
クラウドにOracle Databaseのライセンスを持ち込むときの環境ごとの規定
BYOLがどういうものなのか理解できたものの、「持ち込むにあたってルールはあるのだろうか?」という疑問をもつ方も多いでしょう。
以下では、利用するクラウド環境別に、BYOLを行う際のルールや定義を解説します。
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle社が提供するサービスのOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)を利用している場合、まずは“Oracle Processor Core Factor Table 補足資料”を確認しなければなりません。
この資料に基づき、インスタンスや利用しているエディションを考慮して、適用可否や必要なライセンス数を決定するためです。
OCIのサービスの一つであるIaaSを例に、ProcessorライセンスとNUPライセンスの考え方を見ていきましょう。
まずは、Processorライセンスです。
【OCIのIaaS利用時にProcessorライセンスを持ち込むときの考え方】
| エディション | 保有ライセンス | BYOL可能なOCPU | 注意事項 |
| DB EE | 1 Processor | 2 OCPU | |
| DB SE2
DB SE DB SE1 |
1 Processor | 4 OCPU | エディションごとに上限あり |
上記の表をご覧いただければ、現在保有しているライセンスをクラウドに持ち込んだ場合のリソースがひと目でわかるのではないでしょうか。
たとえば、DB EEで4 Processor持っている方は、8OCPU(物理コア)に、BYOLを行えます。1 OCPUは2 vCPU(仮想CPU)に相当します。
なお、DB EE以外のエディションでは、OCPUやソケットの数によって適用不可な場合があります。
【エディションごとの適用可否】
| 対象インスタンスのOCPU数 | 疑似ソケット数 | DB SE必要ライセンス数 | ||
| DB SE2 | DB SE1 | DB SE | ||
| 1~4OCPU | 1ソケット | 1 Processor | ||
| 5~8OCPU | 2ソケット | 2 Processor | ||
| 9~12OCPU | 3ソケット | 適用不可 | 3 Processor | |
| 13~16OCPU | 4ソケット | 適用不可 | 4 Processor | |
| 17以上のOCPU | 5ソケット以上 | 適用不可 | ||
利用したいクラウドリソースに対して、BYOLで足りない場合は追加購入が必須なため、まずは既存ライセンスの有効活用を検討するとよいでしょう。
こうしたルールを理解して、クラウドにシフトする際の費用試算にお役立てください。
続いて、NUPライセンスを持ち込むときの考え方を、エディションごとに解説します。
DB EEの場合は、Oracle社によって定められた標準ライセンスルールをもとに算出します。
標準ライセンスルールで定められている最小ユーザー数の規定は、25NUPで1 Processorです。
したがって、OCIでは、“25NUP=1 Processor =2 OCPUにBYOL可能”という考え方になります。
DB SE2では、実際に使用しているユーザー数、あるいは最少ユーザー数の10NUPライセンスのどちらか多いほうの数量のNUPライセンスが必要です。
また、インスタンスが8 OCPUを下回る場合も、最少ユーザー数は10 NUPを確保しなければなりません。
参照元:Oracle社
Oracle社から承認されたクラウド環境
Oracle社が承認しているクラウドサービスは、Amazon Web Service・Microsoft Azure Platform・Google Cloud Platformです。
これらをご利用の場合は、ライセンスのBYOLを行えます。
そしてそのルールは、“クラウド・コンピューティング環境におけるOracleソフトウェアのライセンス”によって定義されています。
こちらも、ProcessorライセンスとNUPライセンスに分けて考え方を理解しましょう。
【Processorライセンスを持ち込むときの考え方】
| エディション | 保有ライセンス | BYOL可能な仮想コア(vCPU)数 | 注意事項 | |
| DB EE | 1 Processor | ハイパースレッディングが有効な場合 | 2 vCPU | |
| ハイパースレッディングが無効な場合 | 1 vCPU | |||
| DB SE2
DB SE DB SE1 |
1 Processor | 4 vCPU | エディションごとに上限あり | |
Processorライセンスにおいては、ハイパースレッディングの有無によってvCPUが変わったり、対象が仮想コアになったりするのが特徴です。
また、OCIと同じくDB EE以外のエディションでは、利用の上限がありますので、以下の表をご確認ください。
【エディションごとの適用可否】
| 対象インスタンスのvCPU数 | 疑似ソケット数 | DB SE必要ライセンス数 | ||
| DB SE2 | DB SE1 | DB SE | ||
| 1~4vCPU | 1ソケット | 1 Processor | ||
| 5~8vCPU | 2ソケット | 2 Processor | ||
| 9~12vCPU | 3ソケット | 適用不可 | 3 Processor | |
| 13~16vCPU | 4ソケット | 適用不可 | 4 Processor | |
| 17以上のvCPU | 5ソケット以上 | 適用不可 | ||
一方、NUPライセンスでは、最小ユーザー数の考え方に気をつけたいところです。
DB SE2をNUPで許諾する場合、最小ユーザー数は8vCPUあたり10NUPとなります。
参照元:Oracle社
上記以外のクラウド環境
OCIやOracle社が承認したクラウドサービス以外の環境では、特有の考え方は存在せず、標準のライセンスルールが適用されます。
したがって、オンプレミスのOracle Databaseのライセンスの考え方をご参照ください。
Oracle Databaseの価格
価格の算出方法がわかったところで、実際にOracle Databaseの価格を確認していきましょう。
Oracle Databaseの価格は、オンプレミスとクラウドで異なります。
また、DB EEの場合、追加料金を支払えばオプションを追加することも可能です。
それでは、一つずつ解説します。
オンプレミス
オンプレミスにおけるOracle Databaseのライセンスの価格は、ProcessorライセンスとNUPライセンスで課金の対象が異なります。
Processorライセンスでは、DB EEの場合にCPUコアが課金対象となり、DB SE2の場合にCPUソケットに対して課金されます。
一方、NUPライセンスは、エディションにかかわらず利用する人数が課金の対象です。
先述した“オンプレミスのOracle Databaseのライセンスの考え方”の章を参考に、それぞれ必要なライセンス数を算出し、それに合わせてご購入ください。
なお、ライセンス価格は、ライセンス本体の価格と年間保守価格に分かれています。
【オンプレミスにおけるライセンス本体価格および年間保守価格(2024年9月時点)】
| エディション | ライセンス | 本体価格 | 年間保守価格 |
| DB EE | Processorライセンス | 736万2,500円 | 161万9,750円 |
| Named User Plusライセンス | 14万7,250円 | 3万2,395円 | |
| DB SE2 | Processorライセンス | 271万2,500円 | 59万6,750円 |
| Named User Plusライセンス | 5万4,250円 | 1万1,935円 |
初年度はライセンス本体の価格と年間保守価格の両方が必要になりますが、2年目以降は年間保守価格のみ発生します。
参照元:Oracle社
クラウド
クラウドのライセンスの価格は、“OCPU”という単位で課金されます。
OCIの標準的なデータベースである、Oracle Base Databaseにおいては、以下の4つのサービスオプションから選択する方式となっています。
【Oracle Base Databaseのサービスオプションごとの価格(2025年1月時点)】
| サービスオプション名 | 価格(OCPU/h) |
| Oracle Base Database Service Standard | 33円程度 |
| Oracle Base Database Service Enterprise | 67円程度 |
| Oracle Base Database Service High Performance | 138円程度 |
| Oracle Base Database Service Extreme Performance | 208円程度 |
ライセンス価格に保守費が含まれているので、初年度も2年目以降も支払金額に差異は生じません。
参照元:Oracle社
Oracle Databaseはエディションやライセンスの種類によって考え方が異なる
今回は、Oracle Databaseのエディションやライセンスの種類、そしてそれぞれの算出方法を解説しました。
Oracle Databaseのエディションは、Enterprise EditionとStandard Edition 2の2つです。
また、ライセンスの種類は、ProcessorとNamed User Plusの2つがあります。
これらのエディションやライセンスの種類によって、ライセンス数の考え方や算出方法が異なるため、購入する際は要件や予算を考慮して適切に選択しましょう。
なお、「考え方はわかったけれど、やっぱり複雑で難しい……」という方は、ぜひコーソルへご相談ください。
経験豊富なエンジニアがお客様の要望をうかがい、自社に最適化したOracle Databaseの導入から運用までサポートいたします。