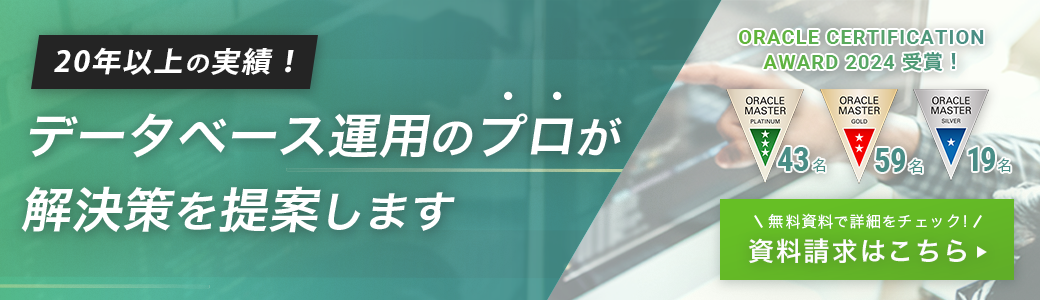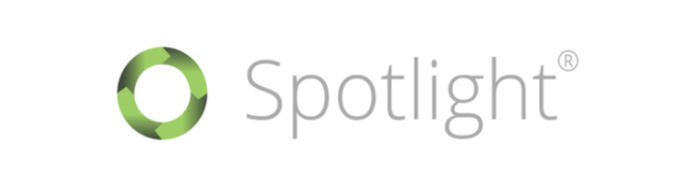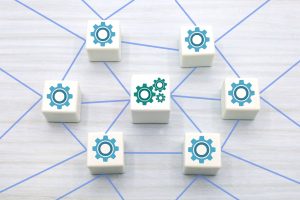システム監視ツールとは、ITインフラの監視に利用されているソフトウェアです。サーバーやアプリケーションなどの稼働状況をチェックして、障害の予兆を発見できます。導入により、監視業務の負担を減らせる点、障害の拡大を防げる点が魅力です。ここでは、システム監視ツールの概要、種類、主な機能、必要性に加え、導入によるメリットや製品の選び方を紹介します。全体像を理解したい方は、参考にしてください。
目次
システム監視ツールとは?
システム監視ツールは、サーバー、ネットワーク、ハードウェア、アプリケーションなどの稼働状況を常にチェックして、さまざまな異常やパフォーマンスの低下を早期に発見するソフトウェアです。簡単に説明すると、ITインフラ全体をまとめて監視するツールといえるでしょう。メリットは、役割が異なる複数の監視ツールを個別に導入する場合よりも、管理の負荷を抑えやすい点です。
システム監視ツールによってできること
システム監視ツールは、各種データを収集して監視対象が正常に稼働していることを常にチェックします。通信障害、過負荷などの異常を検出した場合は、メールやチャットなど、所定の方法で通知します。これらの記録を残して、理解しやすい形で表示できます。以上の流れを自動化できる点も大きな利点といえるでしょう。システム監視ツールを導入することで、負担を抑えつつITインフラ全体を見張れるようになります。異常を早期に発見するとともに、記録したデータをもとに原因を分析したり、改善策を模索したりできる点もポイントです。
そもそもシステム監視はなぜ行うのか
システム監視は、必要性の高い取り組みと認識されています。ここでは、システム監視を行う理由を解説します。
ビジネスの継続性を向上させるため
システム監視の主な目的は、ビジネスの継続性を向上させることです。何かしらの理由でシステム障害が多発すると、顧客からの信頼を失ってしまう恐れがあります。たとえば、取引先も利用する受発注管理システムのダウンは、機会損失や納期遅延などにつながります。ケースによっては、取引先との関係が悪化するでしょう。システム監視を導入することで、本節以降でご紹介するトラブルを予防してビジネスの継続性を高められます。また、システム監視は、災害対策のひとつとしても活用されています。他の対策と組み合わせることで、大規模災害が発生したときに早期復旧を図りやすくなるためです。
障害発生のリスクを軽減させるため
障害の予兆を発見することもシステム監視の目的です。サーバー、ネットワーク、アプリケーションなどを常に監視していれば、CPU使用率が異常に高い、応答速度が遅くなっているなどの異常を早期に発見できます。したがって、システム停止などの大規模な障害が発生する前に対処しやすくなります。これらの取り組みにより、安定した稼働を実現できる点、緊急対応を避けられる点もポイントです。障害を未然に防ぐことも、システム監視の目的といえるでしょう。
不具合による影響を最小限にとどめるため
さまざまな対策を講じていても不具合は起こりえます。発生した不具合が、ビジネスに与える影響を最小限にとどめることもシステム監視の目的です。具体的には、障害の予兆を発見したり、稼働状況やトラブルの履歴を残したりすることで不具合の拡大を防ぎます。記録が残っていると、原因を突き止めやすくなるため、復旧にかかる時間を削減できます。現在の状況をグラフなどで表示して可視化できる点もポイントです(システム監視ツールを導入している場合)。ビジネスの信頼性を高めるために欠かせない取り組みです。
セキュリティを強化させるため
セキュリティの強化も、システム監視の目的です。サーバー、ネットワーク、アプリケーションなどを常に監視することで、不審な挙動を早期に発見して対策を講じられます。ここでいう不審な挙動は、外部からの攻撃だけに限定されません。近年では、内部不正による情報漏えいなどの問題も頻繁に起こっています。他のセキュリティ対策と組み合わせることで、このようなトラブルも防ぎやすくなります。システム監視は、企業の信頼性を高める取り組みです。
システム監視ツールを導入するメリット
システム監視ツールの導入には、さまざまなメリットがあります。主なメリットは次のとおりです。
【期待できるメリット】
- 監視作業の自動化により担当スタッフの負担を軽減できる
- 障害の予兆を発見して障害を未然に防ぐ
- トラブルの原因を突き止めて今後の対策を講じられる
- 蓄積したデータを活用してシステム拡張を検討できる
24時間365日体制でシステムを監視できるため、担当スタッフの負担を大きく削減できます 。人件費などのコストを抑えられる点もポイントです。メリットを実感しやすいツールといえるでしょう。
システム監視ツールの主な機能
システム監視ツールの機能は製品で異なります。ここでは、主な機能を紹介します。
死活監視機能
死活監視機能は、監視対象となるサーバーやネットワークなどの稼働状況を定期的に確かめる機能です。監視により「死んでいるか(=停止しているか)」「生きているか(=稼働しているか)」を確かめるため死活監視機能と呼ばれています。具体的には、Pingコマンドを実行して応答を確認するなどが行われます。死活監視機能の目的は、障害の発生を早期に発見することと復旧作業を迅速に開始することです。この機能を活用して、応答時間の目安を確かめることもできます。
ハードウェア監視機能
ハードウェア監視機能は、システムを構成する物理的な装置や部品を監視して、異常や劣化などのトラブルを早期に発見する機能です。具体的には、サーバーやスイッチ、ルーターの温度やステータスを定期的に確認し、異常を検知時は即座に通知を行います。これらを通して、ハードウェア障害の予兆を発見し、障害となる前に機器交換を行う予防保守が可能となります。
【関連記事】:障害が起こった際に重要なOracle RACとOracle Data Guardを解説
ログ監視機能
ログ監視機能は、監視対象となっているシステムなどのログをチェックして、異常や特定のイベントを検知する機能です。ログは、システムやアプリケーションなどが実行した動作の記録、あるいはこれらに発生した出来事の記録です。具体的には、特定の文字列を発見すると通知する、特定の条件を満たすと通知するなどの役割を担います。どこで何が起きたか、誰が関わっていたかなどをリアルタイムで把握できるため、原因を素早く特定して対応できるようになります。問題解決をサポートするシステム監視ツールの重要な機能です。
プロセス監視機能
プロセス監視機能は、監視対象となっているサーバー上で稼働するアプリケーションなどの動作(=プロセス)をチェックして異常を発見する機能です。具体的には、プロセスが停止していないか、プロセスにおかしな挙動はないかなどを確認します。これらを発見した場合は、自動で通知するなどの対応を行う点もポイントです。以上の働きにより、アプリケーションの動作異常を迅速に発見できます。また、復旧にかかる時間も短縮できるでしょう。サーバーの稼働状況だけを監視していてもトラブルは防げません。プロセスの監視も、システムの安定的な稼働に欠かせないと考えられます。
パフォーマンス監視機能
パフォーマンス監視機能は、CPUやメモリ、ディスクなどの使用率をチェックする機能です。例えばCPUやメモリの使用率が高いと、システムの処理速度は低下します。これにより利用者の満足度が低下する恐れがあります。これらを防ぐため、様々な使用率を監視し、蓄積したデータで使用状況推移をチェックしながら必要に応じて当該機器のスペックを見直すといった対応を行います。ビジネスの信頼性に関わる重要な機能といえるでしょう。
【関連記事】:データベースの監視項目と監視をするメリット・デメリットについて
システム監視ツールの種類
システム監視ツールには、さまざまな種類があります。主な分類方法は以下のとおりです。
【分類方法】
- 監視方法による分類
- 価格による分類
ここでは、以上の分類方法に基づき、システム監視ツールの種類を紹介します。
監視方法による分類
システム監視ツールは、監視方法により次の2つに分けられます。
【分類】
- エージェント型
- エージェントレス型
それぞれの概要は以下のとおりです。
エージェント型
監視対象に専用ソフト(エージェント)をインストールして、内部から監視するものをエージェント型といいます。監視ツールとエージェントで通信を行う点が特徴です。具体的には、エージェントが集めた情報を、監視ツールへ送信することで監視を行います。主なメリットは、状態を詳細に把握できることとネットワークがダウンした場合でも継続して情報を収集できることです。ただし、監視対象に依存して動作するためパフォーマンスに影響を与える可能性があります。導入時、更新時の負担が大きい点や専用ソフトをインストールするためセキュリティ上のリスクが高い点にも注意が必要です。
エージェントレス型
監視対象に専用ソフト(エージェント)をインストールせず、外部から監視するものをエージェントレス型といいます。監視対象のシステムに組み込まれている機能やICMP、SNMPをはじめとするプロトコルを利用して監視に必要なデータを集めます。主なメリットは、導入時や更新時の負担を抑えやすいことと監視対象のパフォーマンスに影響を与えないことです。ただし、詳細な情報は把握しにくい傾向があります。ネットワークがダウンすると、監視を行えない点もポイントです。エージェント型とエージェントレス型の特徴は異なるため、目的などを踏まえて選択しましょう。
価格による分類
システム監視ツールは、コストにより次の2つに分けられます。
【分類】
- 有料版
- 無料版
それぞれの概要を解説します。
有料版
有料版は、初期費用や月額利用料などがかかるタイプです。一定のコストは発生するものの、無料版に比べて機能は充実している傾向があります。原則として、導入時や運用時に専門家のサポートを受けられる点も魅力です。社内に専門家がいない場合でも、問題なく導入、運用できる可能性があります。ただし、具体的な機能やサポートは製品で異なります。不要な機能を搭載しているケースや十分なサポートを受けられないケースも少なくありません。自社のニーズを満たしていることを確かめてから導入することが大切です。
無料版
無料版は、初期費用や月額利用料などがかからないタイプです。コストをかけずに利用できる点が最大のメリットといえるでしょう。無料版の中には、オープンソースソフトウェアもあります。専門知識があれば、自社の環境にあわせてカスタマイズすることも可能です。ただし、充実したサポートは原則として受けられません。導入や運用には、一定の専門知識を要します。適切に管理できないと、想定通りに監視できなかったり、セキュリティ上のリスクが高まったりするため注意が必要です。自社で導入、運用できることを確かめてから利用しましょう。
システム監視ツールの導入で起こりうるリスク
システム監視ツールには気をつけたいリスクもあります。代表的なリスクは以下のとおりです。
運用に手間がかかる
システム監視ツールの運用には、一定の手間がかかります。一例として、監視対象に導入した専用ソフトウェアの更新があげられます。具体的な手間は、導入するシステム監視ツールの種類で異なります。たとえば、SaaSであれば、メンテナンスの手間を大幅に軽減できます。運用にかかる手間を確かめてから導入することが大切です。また、ツールは利用者全員が同水準で操作できるのが理想ですが実際はそうではありません。操作に関してマニュアルや操作ガイドが用意されているかも確認しておきましょう。
十分なサポートを受けられない場合がある
サポートの範囲、内容は、システム監視ツールを提供しているベンダーで異なります。必要最低限のサポートしか提供していないところもあれば、充実したサポートを提供しているところもあります。十分なサポートを受けられないと、発生したトラブルを社内で解決できない恐れがあるため注意が必要です。必要なサポートの範囲、内容は、ケースにより異なります。一般的に、無料版はきめ細かなサポートを受けにくい傾向があります。
システム監視ツールを導入する際に見るべきポイント
続いて、システム監視ツールを選ぶ際に意識したいポイントを解説します。
ポイント①監視状況を可視化できるのかを確かめる
監視状況をグラフなどで表示できると、これまでの推移状況、直面している問題を一目で把握できます。現在の状況を可視化してトラブルに素早く対処するため確認しておきたいポイントです。ただし、具体的な可視化の方法は製品で異なります。自社の希望にあわせてカスタマイズできるものを選ぶと、ストレスを感じることなく運用できる可能性があります。
ポイント②監視項目の取得範囲を確認する
システム監視ツールの監視項目も必ず確認しておきましょう。製品により取得範囲は異なるためです。たとえば、同じサーバー監視であっても、具体的な監視項目は異なることがあります。自社のニーズと照らし合わせておくことが大切です。
ポイント③サポートの手厚さをチェックする
サポートの範囲と内容を確認しておくことも欠かせません。適切なサポートを受けられないと、導入や運用に支障が生じる恐れがあるためです。たとえば、決められた期間で設定する必要があるにもかかわらず、エラーが発生して期間内で設定が完了しないなどが考えられます。自社に専門家がいない場合は、導入前から導入後まで切れ目なく手厚いサポートを受けられる製品を選んでおくと安心です。
ポイント④運用のしやすさを確認する
自社にとっての運用のしやすさを確認しておくこともおすすめします。システム監視ツールを実際に導入すると、さまざまな設定や操作を行わなければなりません。優れた機能を搭載していても、運用しにくい製品は担当者などに大きな負荷をかけてしまいます。結果的に、社内に定着しないことも考えられます。直感的に操作できるなど、使いやすいものを選ぶことが大切です。
システム監視ツールとはITインフラを監視して障害を防ぐツール
ここでは、システム監視ツールについて解説しました。簡単に説明すると、サーバーやアプリケーションなどをチェックして、異常やパフォーマンスの低下を発見するソフトウェアです。主な機能として、死活監視機能、ハードウェア監視機能などがあげられます。導入により、監視作業の負荷を軽減でき、トラブルを未然に防げる点が魅力です。システム監視ツールには、エージェント型、エージェントレス型など、さまざまな種類があります。監視項目やサポートなどを確認して、自社のニーズを満たせる製品を選ぶことが大切です。